 ■ 瀬田川から宇治川へ 滋賀県大津市〜京都府宇治市/宇治田原町
■ 瀬田川から宇治川へ 滋賀県大津市〜京都府宇治市/宇治田原町 ■ 瀬田川から宇治川へ 滋賀県大津市〜京都府宇治市/宇治田原町
■ 瀬田川から宇治川へ 滋賀県大津市〜京都府宇治市/宇治田原町
淀川インデックス
琵琶湖から瀬田川へ/石山、南郷/瀬田の峡谷/瀬田川から宇治川へ/天ヶ瀬ダム
宇治/澱川のはじまり/伏見/三川合流/摂津と河内を境する北水
大阪市へ/十三大橋周辺/最下流の橋梁群/海へ
淀川トップ/サイトトップ
■ 笠取
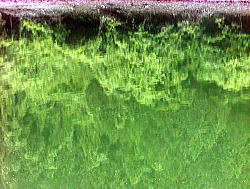 瀬田川は山間部の峡谷で県境を迎える。
瀬田川は山間部の峡谷で県境を迎える。
滋賀県大津市大石曽束と京都府宇治市二尾の境から喜撰山の手前まで、川の真ん中が県境となる。
右岸が京都府、左岸が滋賀県の区間は3kmほど続く。
ここが瀬田川から宇治川への移行帯と言える。
川は既に天ヶ瀬ダムの影響で流れが淀み、湛水域となる。川面を覗き込むとゆっくりとした流れが見える。
川はここから山間部をくねくねと激しく曲折して流れてゆくこととなる。
 |
 |
| 3号大津南郷宇治線・二尾橋から | |
植生は植林杉が多い。このあたりの河畔には水位の変化に強いヤナギが多く生える。道沿いにはクズが旺盛に繁茂し、木に絡み付いてジャングルの如き態である。
■ 曽束
 瀬田川から宇治川への移行帯に架かる橋・曽束大橋。
瀬田川から宇治川への移行帯に架かる橋・曽束大橋。
白いアーチ橋で、緑の峡谷に映える形のよい橋だが、大型車が通るとよく揺れる。
このたもとには支流・曽束川が流れ込んでくる。
川沿いの道はこの橋を渡って左岸側へ移り、右岸には道はなくなる。
この橋の架かっているあたりには、ダムができる前は渡船があった。川の上に渡したロープを手繰る方式のものだったという。
 |
 |
| 曽束大橋から上流方向 | 曽束大橋から下流方向 |
 |
 |
| 蛇行で奥が見えない谷 | 枯木の突き出した水面 |
水面は静まり返り、谷の木々を映す。
霧がかかった谷は深山幽谷の気配を漂わせる。
車両の通行も少なく、人の姿もほとんど無い。
■ 喜撰山
曽束大橋の次に架かるのは喜撰山大橋。これが架かる頃には完全に京都府となり、名は宇治川に移行する。
喜撰山大橋はこの上の揚水発電所に通じる道に架かる。一般人は立入禁止。
川は相変わらず静かな水面を見せている。
 |
 |
| 発電所取水口 | 喜撰山大橋 |
 |
 |
| 漣たつ川面 | 喜撰山 |
喜撰山はそのかみ六歌仙の一人・喜撰法師の隠棲地とされた山。
源氏物語で、八の宮が帰依する阿闍梨の御山もかくあったかと思われる雰囲気。
この雅な名はお茶の銘柄にも使われる。
■ 大峰橋
喜撰山大橋から3kmほど川沿いに下ると、吊橋が架かっている。大峰橋といい、車両は通行禁止。対岸には杣道じみた道があるが、入れるか・どこへ通じているかは不明。
このあたりまで下ってくると山はいくぶん険しさがとれ、谷も少し開けてくる。
植生は雑木の山で落葉広葉樹が多く、紅葉期には山気を吸って鮮やかな錦繍の景が谷を彩る。
この先、宇治川は田原川を左岸に入れて向きを北西に振り、天ヶ瀬ダムへ向かう。
 |
 |
| 大峰橋 | 大峰橋から下流方向 |
 |
 |
| ダム湖に突き出た電柱 | 川面に垂れかかる木 |
大峰橋下には古い様式の電柱が水面に頭を出しているのが見られる。まだ碍子もしっかり付いていて、ダムに沈む以前の顔がちらりと覗く。
天ヶ瀬ダムの前にあった志津川ダムは大峰ダムともいったから、このあたりも何度も改変を受けているのだろう。
大峰橋近くには旅館や喫茶店が点在し、かつての賑わいを偲ばせる。国内観光の不振のゆえか、閉めてしまっているところもある。
| 峡谷の晩秋 | |
 |
 |
| 峡谷の山々には雑木も多い 晩秋には黄色やオレンジの錦繍が谷を染める 植林杉とのコントラストも美しい |
|
*瀬田川・宇治川沿いを歩く方に注意
道は基本的に車道で、車はかなり飛ばしています。爆音を立てて走る暴走気味の乱暴者も出ます。ブラインドコーナーも多く、音もなくカーブを回ってくる自転車もあり、非常に危険です。また、公共交通機関はほとんどありません。曽束から志津川にかけては飲食店はおろか自販機も碌にありません。